今月 岡山で開催される第68回日本糖尿病学会 年次学術集会の 講演/発表 抄録集が閲覧可能になりました.
参加登録済みでないと閲覧できないので,とりあえず登録を済ませて 事前予習がてら ざっと眺めているところです.
注目の食事療法に関するシンポジウム19『糖尿病診療ガイドライン2024に基づく最新の食事療法のエビデンスと指導法』は,単なる新ガイドラインの解説というだけではありませんでした.
というよりも,この記事にも書いたように,依然として 『糖質制限食は絶対に認めない』というスタンスの人が まだまだ学会内部には存在するのだな,と感じさせる講演内容です. この講演については 実際に聴講参加してから詳細な感想記事を書きたいと思います.
今回の学会では,後日 WEB視聴が可能になるのは,教育講演だけです. つまり,特別講演・シンポジウム・口演発表・ポスター発表など,ほとんどすべては 当日の会場で選択するしかありません. つまり3日間の会期中,ごく一部の講演・発表を聞けるだけなのです.
こうなると,症例報告(口演・ポスター)は すべてあきらめざるをえません. なので,上記の抄録集に掲載された すべての口演・ポスター発表(全 1,300件ほど)に目を通しました.
以前から注目しているイメグリミンの発表は,約40件ほどでした. おおまかに言えば,『イメグリミン投与により HbA1cを1%ほど低下させられる』,この効果は確実なようです. ただし これは 他の糖尿病経口薬に比べれば,特に強力な効果とは言えません. したがって,併用投与(DPP-4阻害薬などと)している例も多いようです. また,現時点では,イメグリミンに特有の際立った特徴というものも見出されていないようです. わずかに『イメグリミン投与により インスリン分泌能が改善されることを CPIの増加で確認した』という報告が3件ありました(Ⅱ-85-5, Ⅱ-119-5, P-47-6).
薬物療法の症例報告では,やはり GLP-1受容体作動薬,及びチルゼパチド(商品名:マンジャロ)の報告が圧倒的に多いですね. たしかに チルゼパチドを投与すれば,HbA1cと体重とは確実に下げられる,という点で 医師にとっては使い勝手のいい薬です. ただし 実際の投与症例結果を見ると,体重を ゴッソリと下げられるというわけでもなく,効く人には効くのでしょうが,平均的には数kgの体重低下,しかも BMIが高い人でそれくらいですから,あまり効果のない人もいるのでしょうね. 10kg近い体重減少が達成できたという例もありましたが,それは高度肥満の人でした.
ですので,美容クリニックで『マンジャロというやせ薬』を求める人の大半は,そもそも肥満ではない人でしょうから,多分 期待通りの効果は得られないと思います.
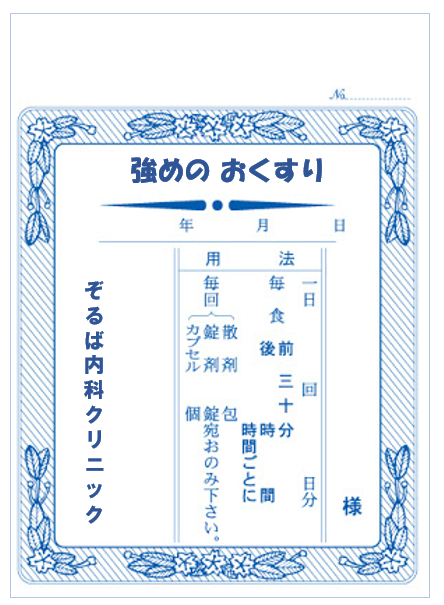


コメント
イメグリミンと言えば、メディカルトリビューンに「イメグリミンの効果に消化器症状が関連か 症状発現例で血糖降下作用大きい」という記事がありましたね。消化器症状が出た方が血糖値がよく下がるということは、腸内環境の変化が重要ということでしょうか。
わたしはプログラム集しか見ていませんが、シンポジウム19「糖尿病診療ガイドライン2024に基づく最新の食事療法のエビデンスと指導法」を見ると、「エネルギー制限食の医学的根拠と実験的指導法」という演題がありますね。その2つ下には山田悟氏も登壇するようです。山田悟氏によれば、たしか「エネルギー制限食はエビデンスがない」ということだったと思いますが、明確なエビデンスが存在するということですかね?(エビデンスがないと言っているのは江部氏でしたっけ)
白井智美氏が「緩やかな糖質制限食のエビデンスと食事指導の実践方法」という演題を出していますが、この「緩やかな糖質制限食」というのは、おそらく「炭水化物40%」レベルの話ですよね?
>消化器症状が出た方が血糖値がよく下がる
この記事にも書きましたが;
https://shiranenozorba.com/2024_06_22_jds67_imeglimin_report/
イメグリミン投与で副作用が出やすいのは 痩せ型の人であり,またそういう人ほど HbA1c低下効果が大きいという傾向は 報告されていますね.
>「エネルギー制限食の医学的根拠と実験的指導法」
【医学的根拠】とは言いつつ,エビデンスと言っていないのは,こういうロジックです.
[肥満はインスリン抵抗性を引き起こす] → [カロリー制限すれば 痩せる] → [インスリン抵抗性が減弱する] → [だから医学的根拠がある]
つまり一般論です.
>白井智美氏が「緩やかな糖質制限食のエビデンスと食事指導の実践方法」という演題
北里大学は 『糖質制限食指導の有効性の検討』という学会発表を10年以上継続してきました. たしか 前回学会で 第12報だったはず. この講演は,これまで北里大学で蓄積した 実症例をまとめて報告するものでしょう.
また白井先生は,昨年の学会で;
Ⅰ-26-3『糖尿病性腎症患者に対するエネルギー制限食指導と糖質制限食指導とでの腎機能低下速度の比較検討』という報告も行っております. なので,カロリー制限食と糖質制限食のどちらが 糖尿病の悪化防止に有効なのかを比較して述べると思います.
>「炭水化物40%」レベル
北里大学の糖質制限指導は,「1食あたり糖質20gから40gと指導」なので,必ずしもC 40%に固定されているわけではないようです.
ああ、白井氏の所属を見落としていました。「緩やかな糖質制限」とはロカボレベルの話だったのですね。
そうか、だから白井氏の演題の次に、山田氏が「追加発言」として登壇するんですね。
なるほど、なるほど。
ぞるばさんのコメントによると、これまでも北里大での実症例を報告しているそうですが、それに対する座長や聴衆の反応はどうだったのでしょう? 糖尿病診療ガイドライン2024では、やっと「炭水化物40%」が認められたものの、ロカボレベルの糖質制限については「6〜12か月の短期間のみ有効」と期限付きの承認ですよね。ロカボはガイドラインに反する食事療法となるわけですが、シンポジウムに採用されるというのは脈アリなのか、それとも矢面に立たせてボロカスに叩くつもりなのか、学会としてはどういう扱いをするつもりなのかが気になるところです。
>それに対する座長や聴衆の反応
北里大学のすべての発表を聞いたわけではありませんが,5,6回は聞きました.全般に座長や聴衆の反応は冷静で,『高齢者は どうしても高蛋白食・高脂質食は苦手. どうしたら糖質制限食をうまく継続できるのか』などという,実務的な質問も出ておりました. 糖質制限に異論・批判を唱える反応は みたことがありません. 普段から口を極めて糖質制限食を攻撃している人が どうしてこういう場に出てこないのか,本当に不思議です.
>シンポジウムに採用されるというのは脈アリなのか
私の解釈では,まだまだその線はないと思います. 学会のスタンスは,あくまでも,C=50-60%のカロリー制限食が『正しい』,ただし やむを得ない場合は 緊急避難的に C=40%を短期間に限って行ってもよい,とこうなのです. つまり どうしても 2013年の『糖質制限食は推奨できない』という提言は守りたいのでしょう. なにしろ 新聞・テレビを呼んで 大々的な記者会見まで行ったのですから,今になって あれを引っ込めるわけにはいかないのでしょう. 少なくとも誰かの目が黒いうちは.
山田氏が一人ディベートをするのではなく、反対派の人と実際にディベートすればいいのにね。
わたしが納得できないのは、糖質制限を反対する理由の一つに「継続できないから」が挙げられる点です。
つまり、「どうせ糖質制限を指示したところで、お前ら(患者)は1年も続かないだろ。だから無駄、無駄」というわけです。
でも、それは食塩制限にも同じことが言えるんですよね。患者に食塩制限を指示すると、3か月ほどは遵守できても、そのうち元に戻ってしまうというデータがしっかり示されています。だからといって、「どうせ食塩制限を指示しても守れないんだから無駄、無駄」とはなっていません。
同じ状況のはずなのに、なぜこんなにも扱いが違うのか。不思議だな〜と思います。
そもそも、「患者に指示しても遵守できない」が反対理由になるのはおかしいですよね。前提が、「患者に無理矢理食事制限を課す」ことになっています。では、患者が自ら進んでその食事制限をやりたいと希望したら? 自ら選んだ食事療法なら、遵守できる可能性は高いですよね。実際、自主的に何年も糖質制限を続けている人はいるのですから。
「どうせ続かないからダメ」というのは、全く理由になっていないと思います。
>反対派の人と実際にディベートすればいい
S19-2でカロリー制限食が提示され,S19-3で糖質制限食の実績が報告されるのですから,当初の企画では,S19-4で両者のDebateが予定されていたのでしょう. しかし,カロリー制限食の側では 誰も土俵に上がろうとしなかったので,やむを得ず 山田先生だけの『独りDebate』になりました,という皮肉ではないでしょうか.
>どうせ続かないからダメ
どの文献の どんな食事療法であっても,必ず 脱落する人はいます.脱落率が示されているということは,逆に言えば継続できた人もいた,ということです.脱落する人がいることを理由にして,継続できている人にまで『直ちにやめろ』と どうして言えるのでしょうか.
この記事にも書きましたが:
https://shiranenozorba.com/2020_07_29_why-jds-diet-therapy-missed-science40/
医者が指示した糖尿病の食事療法を『守っている』と答えた人は35%に過ぎません. この調査は 2009年の「健康日本21フォーラム」で報告されたものですから,まだ 糖質制限食が登場する以前のものです.
当時のことですから,この食事療法とは 食品交換表のことです. 65%の人が守れないカロリー制限食を 当時の医師は指示していたのです.